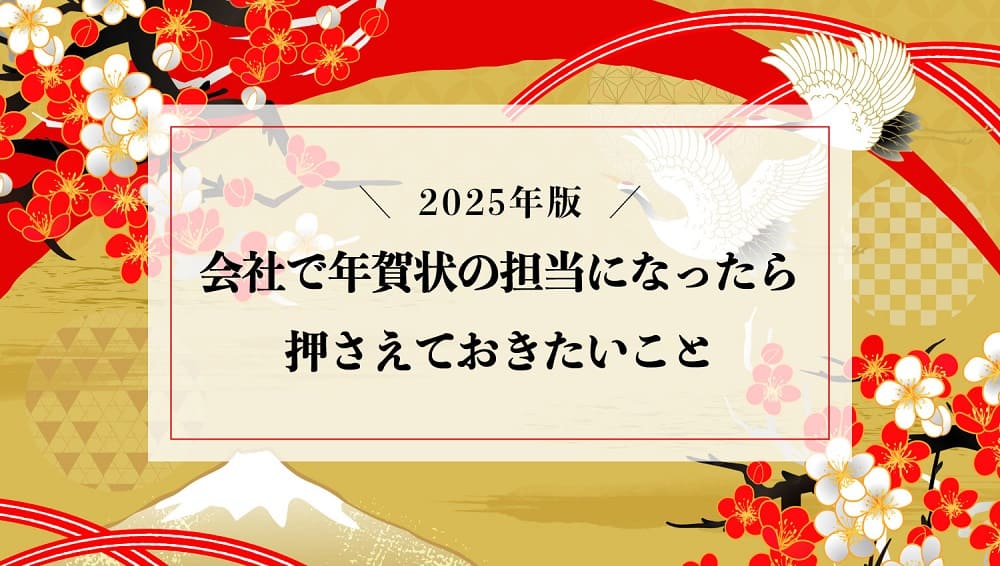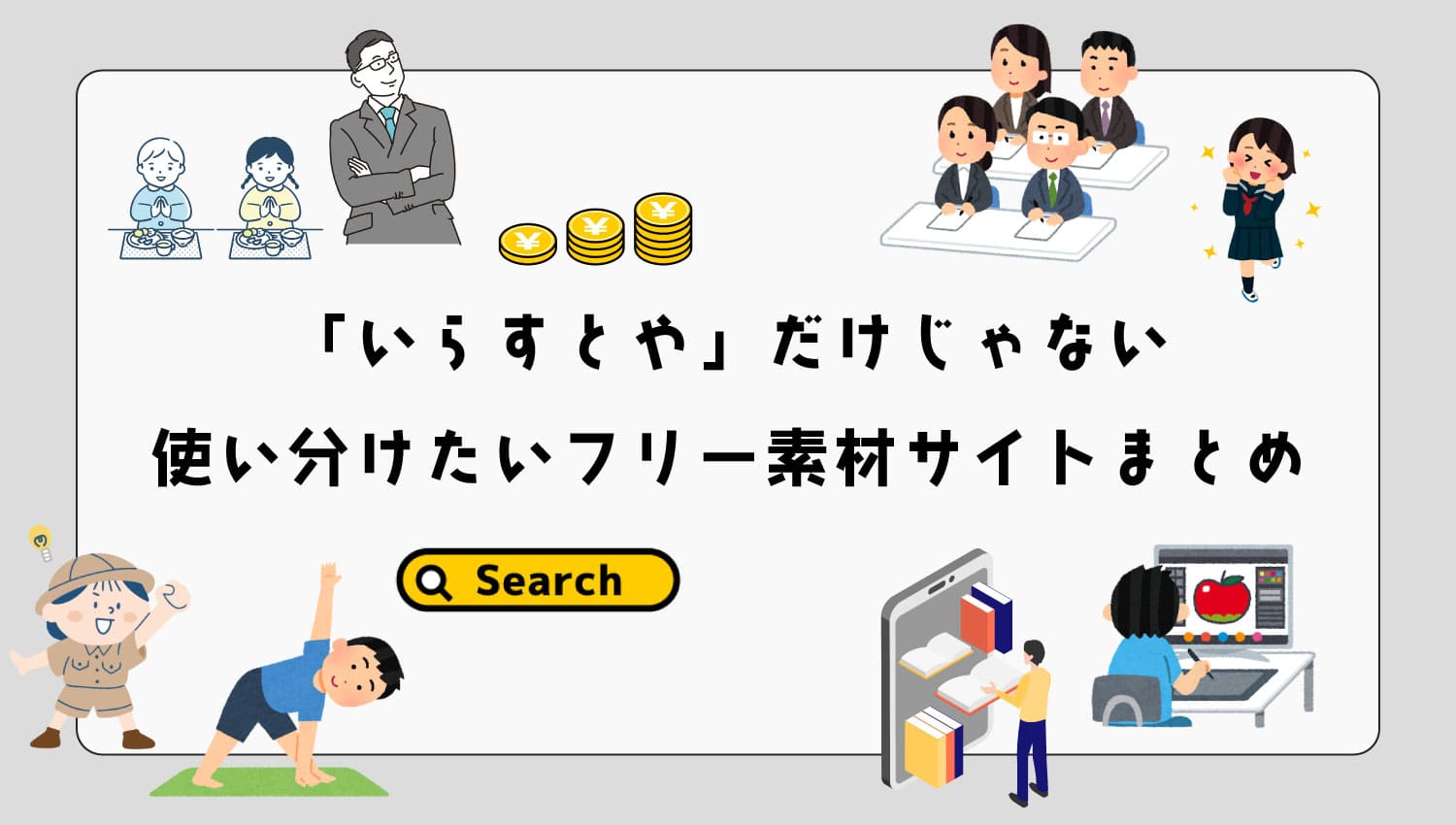2025年の年賀状担当者になったらまず押さえたいこと
年賀状とは、皆様ご存じの通り親しい人やお世話になった方へ新年のご挨拶をするためのものです。
年賀状の起源は古く、平安時代頃に生まれた新年のあいさつ回りをする「年始回り」という文化が簡略化されて年賀状となったと言われています。
企業における年賀状の役割とは
年賀状は個人間だけでなく、取引先や仕事の関係先にも送るのが一般的です。
取引先との良好な関係の構築や企業イメージの向上、情報発信の機会として重要な役割を果たします。
2025年の年賀状の受付期間と郵便料金
2025年の年賀はがきは、販売が2024年11月1日(金)、受付は2024年12月15日(日)から始まります。
元日に届くようにするには、2024年12月25日(水)までに投函してください。
また、2024年10月1日から郵便料金が通常はがき63円から85円と大幅に値上がりしました。
それに伴い、年賀はがきも同様の値上がりとなっています。
1通あたり22円の値上がりですので、大量に発送する企業の年賀状では予算に大きな影響を与えます。
2025年の年賀状は、例年より早めに発送数と予算の確認をするべきでしょう。
2025年用年賀状を作成する流れと進め方
昨年実績からの発送数の把握と予算の確認
昨年の発送数を把握し、大幅な増減がないかを検討し、予算を確認します。
先ほども記載したように、2025年用年賀状からは年賀はがきの価格が大幅に値上がりしていますので注意が必要です。
予算の確保が難しい場合には、オリジナルデザイン作成予定だったものを汎用デザインのものに変える、発送先リストを見直して発送数を再検討してもらうように依頼するなどが必要になってきます。
発注業者選定
発注業者の選定を行います。デザインと印刷どちらも一括で行える業者の方が、担当者の負担は少なくなるのでおすすめです。
例年依頼している業者がある場合にも、今年は郵便料金の値上げ以外にも用紙やインク代、人件費の値上げなどで見積りが上がっている可能性があります。
必ず早めに見積もりを取るようにしましょう。
デザイン作成
デザイン会社が用意している汎用デザインを使用するか、企業のオリジナルデザインを発注するかによって工数が変わってくるので注意しましょう。
企業から送るものであれば、経営者から担当者まで幅広い年齢層の方に届くことを意識してデザインを選定したいですね。
発送先リストの収集
各部門から年賀状の発送先リストを収集する場合には、必ずフォーマットを統一させるようにしましょう。
宛名印字を印刷会社に依頼する場合には印刷会社独自のフォーマットがあるので事前に共有してもらうのがベストです。
また、宛名リストは個人情報になります。社内のプライバシーポリシーに則り、適切な処理をする必要があります。
テレワークやデジタル化が進み、個人情報流出の事案は増えています。
発送先リストを編集する人すべてに重要性を周知させる必要があります。
印刷、発送
デザインと発送先リストが確定したら、印刷へ進めます。
必ず宛名印字をしていない予備も含めてもらうようにしましょう。
営業担当者などは年賀状にコメントを手書きで書きたい方も多いと思います。
師走は年賀状やカレンダーなどで印刷会社も混んでいるため、早めに印刷物が手元に届くようスケジューリングしたいところです。
また、年賀状の元日に届く期限よりも余裕を持って投函するようにしましょう。
「そもそもなぜ年賀状は必要なのか?」あらためて見てみる
年賀状を送らないことで生じるデメリット
個人間では年賀状をもう送っていない。という人も多いかと思いますが、企業が年賀状制度を廃止した時のデメリットを解説します。
顧客関係の希薄化
年賀状でしかやり取りをしていない休眠顧客もいるかもしれませんが、そういった方とのコミュニケーションの場がゼロになってしまうのが一つ目のデメリットです。
筆者も、年賀状のみのやり取りをしていた顧客から年始急に連絡が来て、「年賀状を見て思い出したよ。実はお願いしたいことがあって…」と商談化した経験があります。
企業イメージの低下
若い世代では年賀状がなくなっても気にならない方も多いですが、経営者層や決定権のある世代の方は文化を重んじる場合も多く、年賀状を送ってこないことに対して礼儀や配慮に欠けるイメージを持たれる可能性があります。
競合他社との競争力の低下
自社が年賀状を送っておらず、競合他社が送っていた場合にはどうでしょうか。
休み明けにはメールよりもはがきの方が目に留まりやすい傾向にもあるため、一歩遅れをとってしまいます。
メールなどデジタルでの年賀状の考え方
企業が紙の年賀状をデジタル化する動きは近年ますます加速しています。
印刷代や郵送料が値上がりしている中で、デジタル化することで相当のコストカットが実現できます。
また、宛名リストの収集や印刷、投函締め切りなどに左右されないため余裕を持って新年のご挨拶の準備をすることが出来ます。
年賀状廃止の意見も出てくるかとは思いますが、業種や取引先を考えて慎重に判断する必要がありそうです。
今後、年賀状のあり方はどうなっていくのか
アイスタットが2023年に行った「年賀状離れに関する調査」の結果では、年賀状を出す人の割合が51.3%、出さない人が48.7%でほぼ半々という結果になりました。
また、年賀状を出すと回答した人の中でも47.4%が「そのうちやめたい」、22.7%は「すぐにでもやめたい」と答えており、年賀状を負担だと考えている人が増えています。
特に30代までは新年のあいさつを年賀状ではなくSNSを中心に利用しており、LINEではスマートねんがなどのサービス提供も開始されています。
ビジネスでもそういった流れは出てくることが予想されます。[注1]
年賀状でいいコミュニケーションのスタートを
元日に届くようにするには、2024年12月25日(水)までに投函しなければなりません。
また、郵送料や印刷代は今年特に値上がりしています。早め早めのスケジューリングが必要です。
年に一度の大切なコミュニケーションの機会、年賀状で関係強化につなげてくださいね!
・関連資料のリンク
[注1] 年賀状離れに関する調査/アイスタット